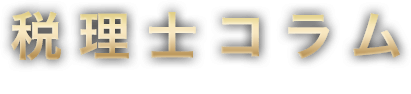「外注費」を支払う場合のチェックポイント
2019.07.26
法人や個人の業務は、外部に委託して行うことができます。
たとえば、ホームページの制作、事務所の清掃や庭木の剪定、会計ソフトへの入力作業、社内のための講演など、外部のプロに委託することが考えられます。
このとき、依頼主である会社や個人事業主は、相手と雇用契約ではなく、業務委託契約などを結びます。
そして相手に支払う報酬は、給与ではなく、外注費や外注工賃、業務委託費などして処理します。
しかし、この外注費などが、「本当は給与に該当するものではないか」という指摘が税務署から行われる場合があります。
今回は、「外注費」を支払う場合のチェックポイントを解説します。
外注費と給与の区別が問題となる理由
そもそも、一体なぜ外注費と給与の区別が問題となるのでしょうか。
理由は、消費税と源泉徴収税の違いにあります。
消費税のルールが違う
消費税の課税事業者は、事業で支払った対価を、課税仕入か否か区別して経理を行う必要があります。
給与は課税対象外となりますが、外注費は課税仕入になります。
なぜこの区別が必要かというと、消費税の納税額が、課税売上によって受け取った消費税額と、課税仕入から計算した仕入控除税額の差額となるため(※)です。
したがって、給与(課税対象外取引)を外注費(課税仕入)であると誤認して処理を行うと、本来納めるべき税額が不足してしまうことになるのです。
(※)簡易課税を選択している事業者の場合、問題になりません。
源泉徴収のルールが違う
「源泉徴収義務者」は、給与や一定の報酬から所得税等を源泉徴収しなければなりません。
給与であれば、その源泉徴収税額は、従業員などから提出を受けた「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容と給与の支給額から、毎月決定されます。
これに対して外注費は、支払相手が個人で、かつ原稿料や講演料などの報酬であって1回の支払いが5万円を超えるもの(※)については、源泉徴収が必要となります。この場合の源泉徴収税額は、支払った報酬の10.21%となり、100万円を超える部分は倍となります。
計算方法が異なるため、給与か外注費かを誤ると、徴収すべき税額にも誤差が生じます。
徴収した源泉所得税等は、翌月10日まで(納期の特例の承認を受けている事業者は、7月10日と翌年1月20日の年2回)に納税しなければなりません。
(※)源泉徴収の対象となる報酬には、ほかにも、個人事業主である士業や外交員、ホステス、専属のスポーツ選手などに支払うものがあります。税額の計算方法はそれぞれ異なります。
外注費と給与の区別が問題となる理由
外注費と給与の区別を誤れば、消費税や源泉徴収税の納税額も誤ることとなります。
特に消費税は、外注費で処理した方が、会社や個人事業主の税負担が軽減されます。
そのため税務署から、本当は「給与」に該当するものではないか?という指摘が税務署から行われるのです。
もし、期限内に納税した税額が、本来納税しなければならない税額より少なかったことが発覚した場合、延滞税や加算税の対象となり、通常より多くの税金を納めなければならないこともあります。
「外注費」を支払う場合のチェックポイント
外注費と給与の区別は、契約の形式、依頼の内容、それに対する仕事の実態などから総合的に判断されることとなります。
依頼内容によってチェックポイントは異なりますが、外注費が給与に該当しないかを区別する共通のポイントとなるのは、
・依頼主からの指揮命令に服していないか
・時間的な拘束が行われていないか
です。
たとえば、清掃を専門業者に委託する場合、委託を受けた業者が清掃用具を持参し、その業者のやり方で清掃を行います。これは依頼主からの指揮命令に服する従業員の仕事とは異なります。
これに対し、講演を委託した場合、当然おおまかな講演内容の打ち合わせは必要ですが、たとえば配付資料などの内容やデザインなど個別の作業を指揮命令するような場合は、外注費とは認められない可能性があります。
また時間を指定して出勤してもらう場合も、ケースバイケースですが外注費とは認められない可能性があります。
外注費の活用は専門家に相談を
外部への委託は、従業員1人を雇うよりも低コストで業務を完遂できることや、依頼主に専門知識やノウハウがなくても安心して任せられるといったメリットがあります。
しかしながら、それを本来、給与を支払うべき相手にまで適用することはできません。
外注費と給与の区別について、今回は税務上の問題をあげましたが、給与に該当する場合、就労時間や雇用期間などによっては社会保険への加入義務も生じるため、最悪の場合、労使問題にも発展しかねません。
外注費か給与か、迷ったときは専門家に相談しましょう。
【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】